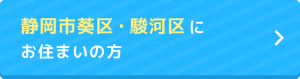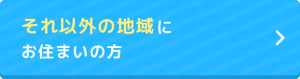- トップページ
- 小学校の教科書は、てごわい
No.01小学校の教科書は、てごわい
小学生のキミ、そして保護者(お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん)に質問。
質問1
次のうち、小学校の教科書に載っている言葉はどれでしょう。
- マスメディア
- メディアリテラシー
- 報道被害
- 捏造(ねつぞう)
- 個人情報
- 著作権
答えは全部。キミの教科書に載っていないとしても、隣の市や町の小学校で使っている教科書には載っている。
小学校で習うのだから、キミの保護者は、上の言葉を全部スラスラと言えるはずだ。では、質問の二つ目。

質問2
キミの周りの大人に、上の単語の意味を聞いて、どんな答えが返ってきたかな?
正直に打ち明けよう。大人のボクも答えられなかった。新聞記者を30年近くつとめていながら答えられない。だから、キミの周りの大人が答えられないのを責めたり、笑ったりしないでほしい。
(「単語の意味」は、記事の一番下に書いてあります。)
なぜキミはメディアを習うのか
個々に並んだ言葉は、すべてメディアに関係する言葉だ。メディアとは、新聞・テレビ・ラジオ、そしてインターネットのサイトのこと。
ボクが小学生ころには、習わなかった。キミの保護者も習っていないだろう。「こんな難しいことを習っているの」とびっくりした親もいるだろう。なぜ、キミの世代で習うことになったのだろう。新聞、テレビ、ラジオはボクの小学生時代にもあった。あのころ無くて、今あるメディアといえばインターネットだ。インターネットが広まった今、小学生のころからメディアをしっかり学ぶ必要ができたからだと思う。
インターネットは便利だけど…
キミが今読んでいるこのページはインターネット。インターネットは、何でも調べることができる。すぐに使える。とても便利だ。
一方で、便利なだけではなく注意が必要と教わったはずだ。正確な情報と、怪しい、危ない情報の見分けがつけにくい。大人もうっかり、ウソのニュースを信じてしまうこともある。
同じ考えに囲まれるのはよくない
インターネットの危険はそれだけではない。深刻なのは自分で気がつかないまま、いつの間にか自分に都合のいいニュースに囲まれているということだ。
フェイスブックやツイッターなどソーシャルネットワーキングサービス(SNS)で、たくさんの友だちができたとする。友だちになった理由は、キミと好みや趣味が共通しているからだ。だから、フェイスブックやツイッターで、友だちが教えてくれるニュースは、キミの意見や好みにとても近くなる。
スポーツには、ドッジボールもサッカーも野球もフィギュアスケートもトライアスロンもあるのに、ドッジボール好きの友だちが勧めてくるニュースばかりを読んでいると、つい、ドッジボールだけが人気スポーツでファンも一番多いと思い込んでしまう。
話し合って意見を変える大切さ
キミが習う国語の教科書には、違う意見の人と話し合うことの大切さがしっかり書いてある。話し合った後に、次の3点を振り返ることを勧めている。
- なるほどと思った友達の意見
- なかなか答えられなかった質問
- 友達の発言によって変化した自分の考え
ボクが特に大切だと思うのが、3の「友だちの発言によって変化した自分の考え」だ。違う意見の人と話し合って自分の考えが変わることは、悪いことでも恥でもなく、いいことなんだ。ドッジボールファンのキミは、フィギュアスケートファンと出会って、話を聞いて、フィギュアスケートファンになるかも知れない。
ちょっと新聞の宣伝
この世の中には、たくさんの意見を持つ人が、それぞれの生き方で生活している。相手の話を良く聞いて、相手を認めて、そして自分の意見も伝えて、変化しあって、お互いが成長する。それがよりよい社会を作ることにつながる。
さまざまな意見に出合うなら、新聞が手っ取り早い。もちろん、このページのようにインターネットにも、さまざまな意見が載っているコーナーもある。これから、このコーナーで、さまざまな意見に触れて、自分の頭で考えていこう。
試読のお申込みはこちら

質問3
保護者と話し合おう。実際に中学校に入試問題として、小学6年生が挑戦した問題を紹介する。大人だって解けない問題だ。
2003年、ホテルを予約しようとしたハンセン病患者団体が「他の客の迷惑」と拒否された。報道されるたびに「調子にのるな」「税金で生活して権利だけ主張するな」と非難の声が寄せられた。
フランスで2017年、男性が女性看護師に暴力をふるう動画と「これが今のフランスだ」というメッセージが拡散。「移民は国へ帰れ」と多くのコメントがついた。しかし、本当はロシアの映像だった。
- 特定の人々に対する感情がコントロールできなくなるのはなぜか。特定の人々に対する感情を説明し、どのようなきっかけで感情をコントロールできなくなるかについて120字で。
- なぜ次々に多くの人々が関わっていったのか。人々の気持ちに注目して、80字以内で。
(問題を一部省略しています)
(麻布中学 2018年社会)
小学校教科書の答え
メディア(マスメディア)
情報を送る方法のことを、メディアといいます。なかでもテレビや新聞などのように、同じ情報を多くの人にいちどに送る方法のことをマスメディアといいます(東京書籍社会5)
マスメディア
新聞・ざっし・テレビ・映画など、情報を多くの人に対して伝達する手段のこと(教育出版国語5)
メディアリテラシー
テレビやラジオ、新聞や雑誌、インターネットなどからの情報をそのまま受け止めるのではなく、自分なりに判断する力のことです(学校図書国語5)
メディアが伝える情報の中から必要な情報を自分で選び出し、内容の正しさを確認し、活用する能力や技能のことをいいます(東京書籍社会5)
報道被害
事実とちがう報道や大げさな報道によって悪者にされてしまうと、うたがいが晴れても生活や仕事に不利益を受けたり、たいへんな心のいたみを受けたりしてしまいます(東京書籍社会5)
捏造(ねつぞう)
事実でないことを事実であるかのようにうそをついてつくりあげること(日本文教出版社会5)
個人情報
氏名、住所、生年月日、以前の治療の記録など、その情報によって特定の人がわかってしまう情報のことです。個人情報がもれると、犯罪にまきこまれるなどの被害につながるおそれがあります(東京書籍社会5)
その人が誰であるかが分かってしまう情報のこと。住所・氏名・年齢・生年月日・電話番号・顔写真など、さまざまな情報がこれに当たる(光村図書社会5)
本人を特定できるあらゆる情報のこと。住所、氏名、年齢、性別、生年月日、電話番号などが基本的な個人の情報です。これら以外にも、国籍、家族構成、勤務先、趣味、身長、体重、血液型など、さまざまな情報が個人情報にあたります(日本文教出版社会5年)
著作権
文章や絵、音楽、写真などは著作物といって、作った人に著作権という権利がある。ホームページを作るときは、他の人がかいた文章や絵、とった写真などを勝手に使わないようにしよう(光村図書社会5)
みんなの意見を見てみよう
「#ターくんと頭ぐるぐる」のハッシュタグを検索して、SNSに投稿されたみんなの意見を見てみよう。